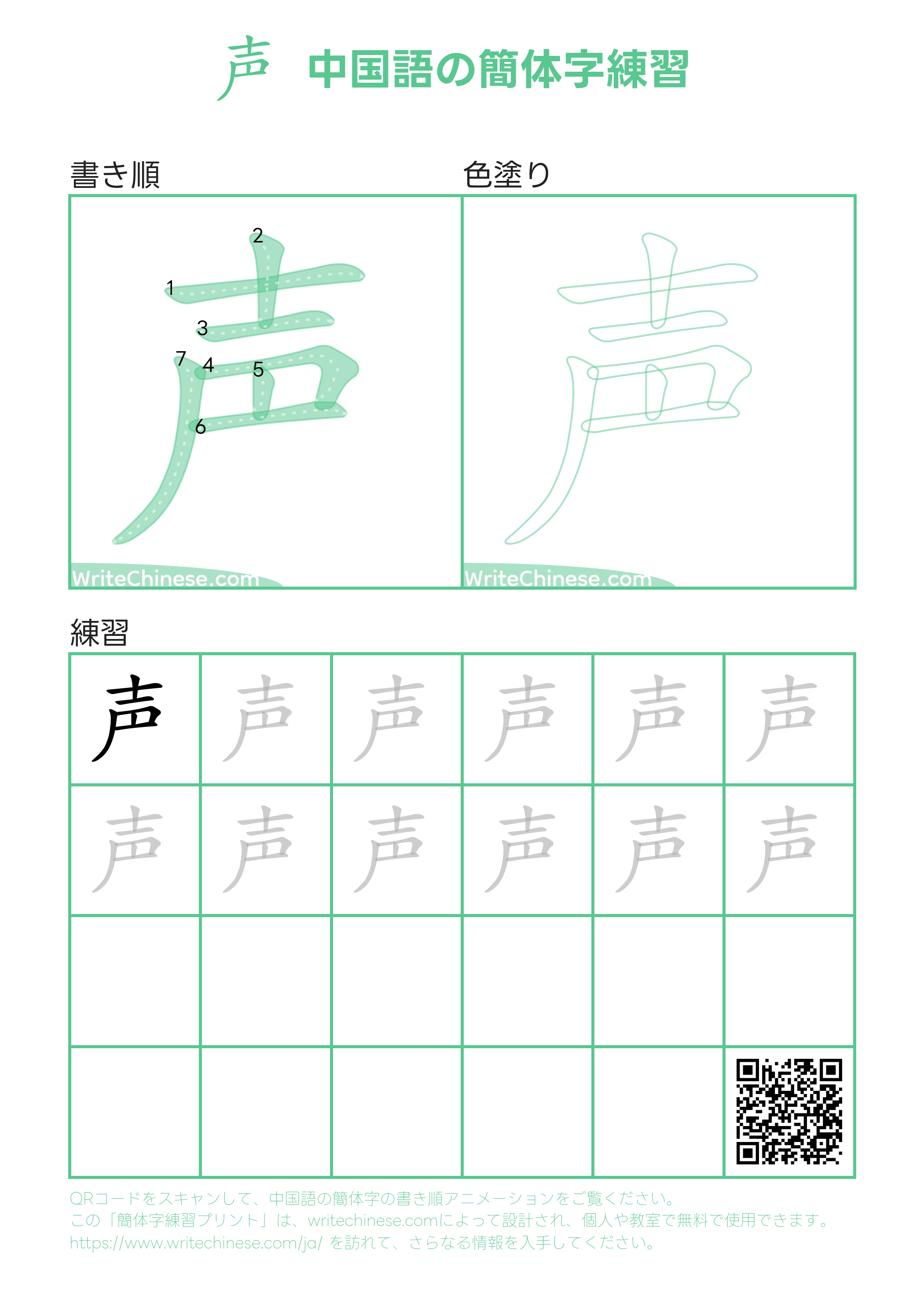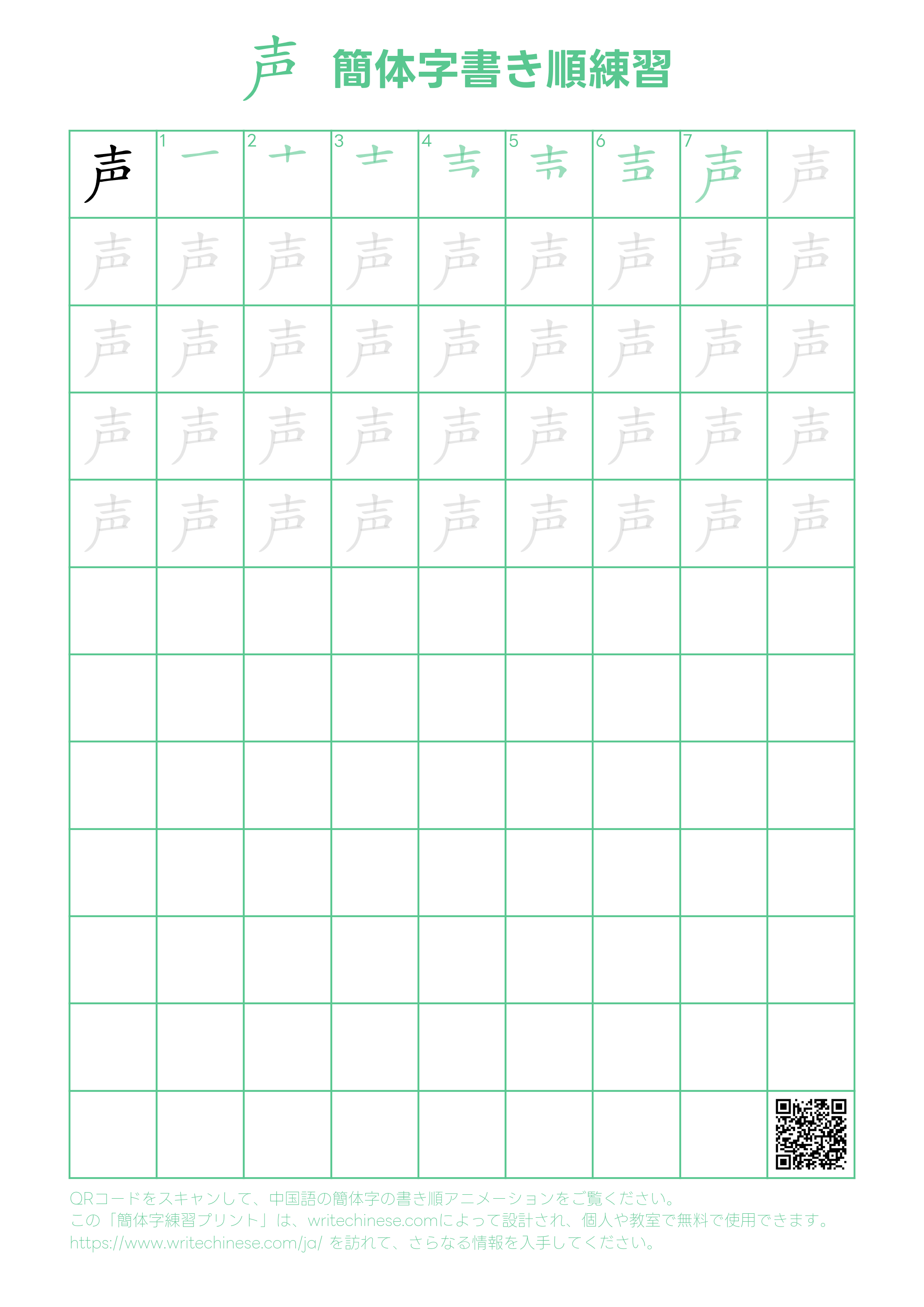「声」の書き方
筆順(書き順)アニメーション
中国語の簡体字「声」の筆順アニメーションを見て、「声」という漢字の書き方を学びましょう。
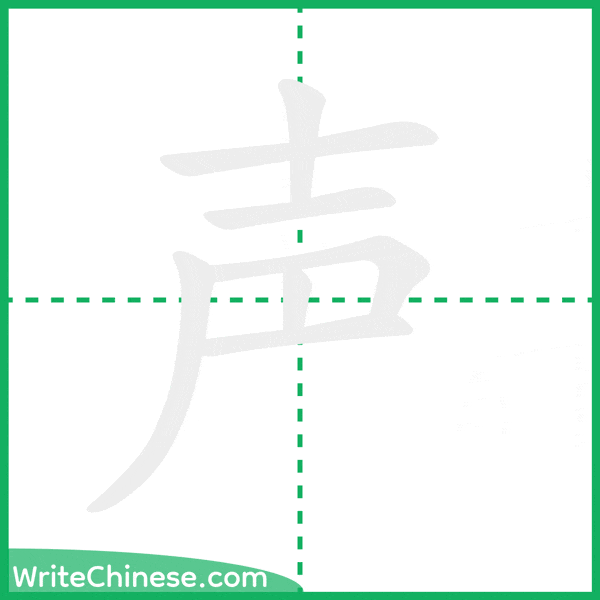
一画ずつ:声の書き順
視覚的なステップバイステップの指示を使って、中国語の漢字「声」の書き順を一画ずつマスターしましょう。
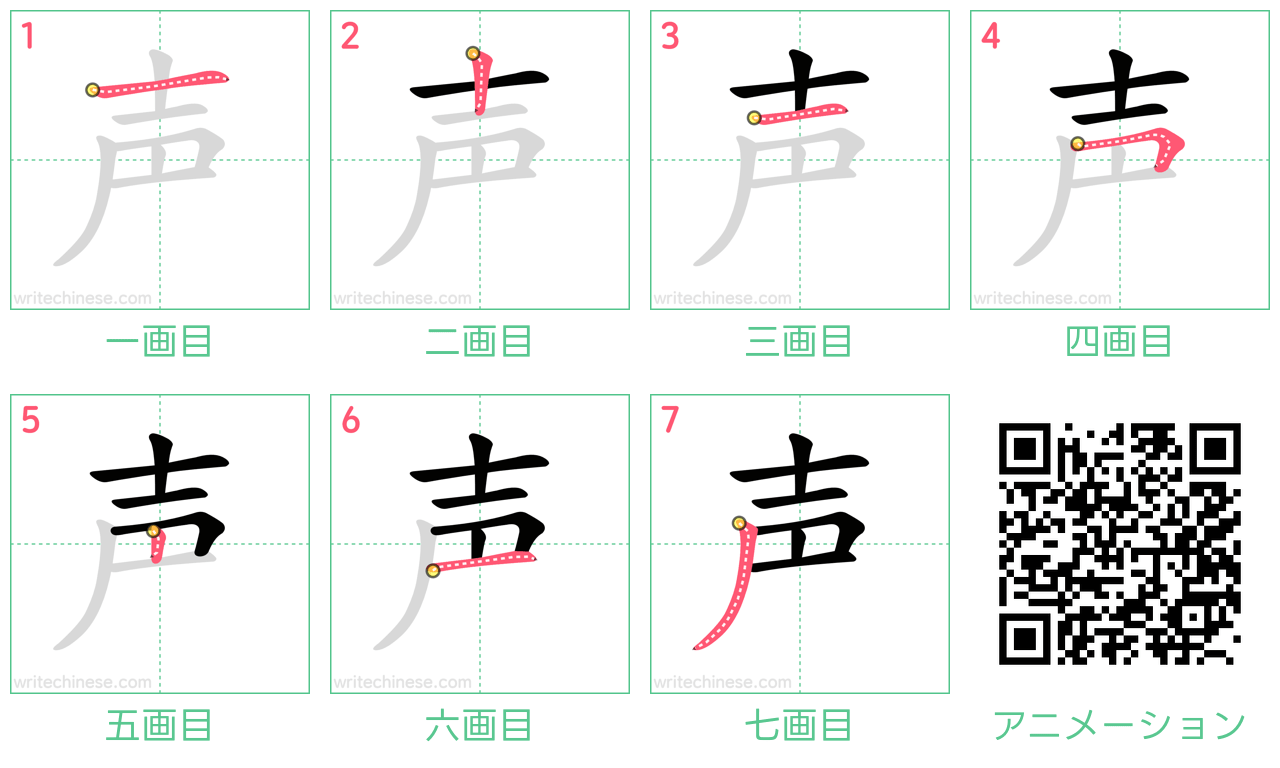
書道の達人に従って、一歩ずつ「声」を書いてみましょう
書道の先生によるビデオチュートリアルで、中国語「声」の正しい書き方を学びましょう。書道の達人によるステップバイステップのガイドに従って、中国語「声」を書きましょう。以下の印刷可能な手書き用のワークシートをダウンロードして、ペンと紙で一緒に書く練習をしましょう。
無料の印刷可能な「声」の手書き練習用ワークシート
「声」の部首・画数・読み方・意味など
ピンイン
shēng
部首
士
画数
7
英語
sound / voice / (a measure word, used for sounds) / tone / noise
使用頻度
★★★★★
声
聲 shēng
〈名〉
【本义】:声音;声响
【造字法】:形声。从耳,殸( qìng)声。“殸”是古乐器“磬”的本字,“耳”表示听。
【日】
1 物体が振動するときに生じる、聴覚を引き起こす波。
2 ニュース、音信。
3 口に出して知らせること、言いふらすこと、主張すること。
4 名声。
5 音楽や歌舞。
声
聲 shēng
〈名〉
【日】
1 同本義 ([En.] sound;voice)
【引】
1 《説文》:声、音なり。
2 《礼記·楽記》:物に感じて動く、故に声に形をとる。
3 《虞書》:声、永律に依り和声す。
4 《礼記·郊特牲》:凡そ声は陽なり。
5 《詩·齐風·鶏鳴》:蠅の声。
6 《詩·小雅·車攻》:聞くに声無き者。
7 柳宗元《永州八記》:水の声を聞きて、佩環の鳴るがごとく、心楽なり。
8 唐・白居易《琵琶行(並序)》:声を尋ねて暗に問う、弹者は誰ぞ。琵琶の声止まるに語るは遅し。
9 《孟子·梁惠王下》:百姓、王の鐘鼓の声、管楽の音を聞く。
【例】
また、声叉(声が正常でない); 声嘶(声がかすれた); 声如洪鐘(人の話し声が大鐘の音の如き); 声振林木(歌声の高亢清遠、林木を揺るがすのに足る); 声動梁塵(歌声が洪亮動人)。
音楽、詩歌
【日】
1 音楽;詩歌 ([En.] music;poet)
【引】
1 《詩·大雅·皇矣》:声を大にして色を賜ること無し。
2 《史記·廉頗蔺相如列伝》:趙王はひそかに秦王が秦声を巧みにすることを聞く。
3 《孟子·梁惠王下》:声、耳に聞こえ不足なりや?
【例】
また、声色貨利(音楽、女色、貨物、財利。かつての支配階級が求めた物質的享楽を指す); 声詩(楽歌); 声塵(音楽)。また、古代の指揮作戦のための鈸、銅、鼓などの楽器の声を特に指す。
声望、声名(名声)
【日】
1 声望、声名 ([En.] reputation)
【引】
1 《詩·大雅·文王有声》:文王有り声あり。
2 《孟子·離婁下》:故に声、情を超え聞こえたり、君子はそれを恥とす。
3 《呂氏春秋·過理》:臣は古人が天下を辞し恨み色無き者につい声を聞き、その実を王に示すと聞く。
【例】
また、声気(名声;名気); 声名煊赫(名声顕著); 声芳(良き名声); 声施(名声が流布する); 声烈(著名なる名望); 声名人(名望のある人); 声位(名声と地位)。
口信;消息;伝説
【日】
1 口信;消息;伝説 ([En.] information;news)
【引】
1 《漢書·趙廣漢伝》:界上の亭長、声を寄せて我に謝す、何以か為しあらん、致問せざるを。
【例】
また、声伝(伝聞の事); 声論(舆論); 声聞(音信、情報)。
声威;声勢
【日】
1 声威;声勢 ([En.] renown;prestige)
【引】
1 《戦国策·齊策》:声威天下。 注:“勢也。”
【例】
また、声教(声威と教化); 声焰(声勢の気焰); 声振寰宇(名声威勢が天下を振動させること。形容声威が極盛であること)。
声調
【日】
1 漢字の声調 ([En.] tone)
【例】
如:声病(詩、詞、曲の声調、平仄、規定された律則、標準に合わない); 声颡(腔調); 声律(詩文の声韻と格律); 声比(音調相和); 声文(音調を一般に指す); 声曲(音声曲調); 声度(声調のこと); 声客(声調の意)。
言語、口音
【日】
1 言語、口音 ([En.] speech)
【引】
1 明・魏禧《大鉄椎伝》:人とあまり言わず、語は楚の声。
【例】
また、声嗽(言語)。
声母
【日】
1 漢字の声母を指す。(漢字の音節の始まりの音)
【例】
如:声旁(漢字の形体の分析用語。形声字の構造における発音を示す部分で、形旁と対になる); 声纽(音韻学用語。すなわち声母。漢字音節の始まりの子音); 声符(すなわち声旁)。
声
聲 shēng
〈動〉
【日】
1 発声する ([En.] make a sound)。
【例】
如:不声不响; 声張(声を上げる;張扬); 声哄(騒がしい); 声咳(咳の声); 声唤(呻吟し、苦痛ゆえに叫ぶ); 声屈(冤を訴える)。
声称、宣扬
【日】
1 声称する、宣言する ([En.] claim)
【引】
1 明・張溥《五人墓碑記》:吾社の為す行動、士の先者のために、声義なり。
【例】
また、声云(声言の意); 声兵(出兵を告げる); 声述(声明する明記); 声叙(明確に述べる)。
吟咏、楽歌
【日】
1 吟咏する; 僅柱する ([En.] sing)。
【例】
如:声伎(歌舞などの技芸)。
聞く
【日】
1 聞く ([En.] hear)
【引】
1 清・潭嗣同《仁学》:目で色を得ず、耳で声を得ず、口鼻で臭味を得ず。
声
聲 shēng
〈量〉
【日】
1 声が発生する回数の単位 ([En.] time)
【引】
1 唐・白居易《琵琶行(並序)》:転軸、弦を張ること三、二声、曲調を成す前に情あり。
【例】
また、数声のほくそ笑み; 数声の鳥の鳴き声。
ピンインが似ている漢字のリスト
部首が同じ漢字のリスト
アクセスの容易化
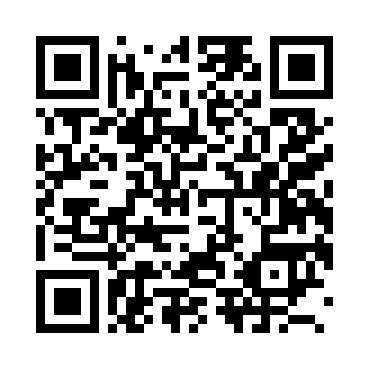
ウェブサイトのアドレスを覚える必要も、中国語の文字を入力する必要もありません。QRコードをスキャンするだけで、このページに簡単にアクセスできます。または、URLをクリックしてコピー&ペーストすることでも、このページに素早くアクセスできます。
「声」の文字コード(入力方法)
ピンイン
sheng1
五筆
fnr
倉頡
gah
鄭码
bxm
四角番号
40207
Unicode
U+58f0
漢字を画数から検索
HSKの級から検索